news
食品表示法とは?【食品工場の用語解説】コラム
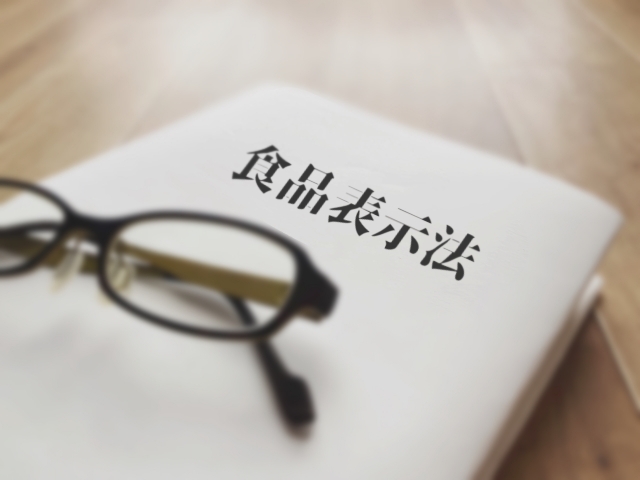
食品を選ぶ際に、その安全性を判断する上で欠かせないのが「食品表示」です。その表示基準を定めている「食品表示法」について、食品業界に関わる人は理解しておく必要があります。そこで、この記事は食品表示法とは何か、目的、8つのポイントについて解説しています。
食品表示法とは?
食品表示法とは、消費者が安全で身体によい食品をわかりやすく選べるように、食品の安全性や機能性に関する表示を定めた法律です。
従来、食品表示に関する規則は複数の法律によって定められ、理解しにくい状態でした。この問題を解決するため、食品衛生法、JAS法(日本農林規格等に関する法律)、健康増進法における食品表示に関する法律を統合し、業界関係者と消費者の両方にとって分かりやすい「食品表示法」を導入しました。この新しい法律は、2015年4月より実施されており、原産地表示や制度、その他の法令に関する規定も含まれています。
食品表示法の目的
食品表示法の目的は、食品を食べる際に安全を確保し、消費者が自分で考え合理的に選べるようにすることです。この法律は、消費者の利益を高めることで国民の健康を守り、向上させ、食品の生産と流通をスムーズに進めることを目指しています。また、消費者のニーズに応える形での食品生産を促進し、それに貢献することも重要な目的です。これにより、消費者が食品表示を確認し、適切に管理できるよう支援します。
食品表示法には、jas法(日本農林規格等に関する法律)と密接に関連する規定も含まれており、表示内容の適正化を図っています。
食品表示法のポイント
食品表示法の主なポイントについて8つ解説します。
①機能性表示ができる
野菜や果物といった生鮮食品、加工された食品、サプリメント等が、健康維持や向上に役立つ具体的な効果(機能性表示)を示せるようになりました。この表示を行うためには、表示内容や事業者の基本情報(名前や連絡先など)、安全性や効果の根拠、生産や品質管理の情報、健康被害への対応体制など、必要な情報を販売予定日の60日前までに消費者庁へ報告することが責任として求められます。また、これらの事項を適切に管理し、表示の信頼性を確保することが重要です。
②原材料と添加物を区別する
これからは、消費者が購入する食品について、原材料と添加物をより明確に区別できるように、「添加物」というラベルをつけて分かりやすく表示することが求められます。これまでのJAS法に基づく品質表示基準では、原材料と添加物を区別せず、重量の多い順に並べて表示することが一般的でした。しかし、今後は他の加工食品と同じ基準に基づいて、原材料と添加物を明確に区別し、それぞれを重量順に表示するように統一されます。これにより、消費者は食品の成分についてより詳細な情報を得ることができ、選択の幅が広がります。
さらに、原材料を単に混ぜ合わせたような加工食品においても、大きな変化がない複合原材料を使用する場合には、構成する原材料を個別に表示できるようになるため、消費者に対してより正確で透明性のある情報提供が可能になります。これにより、消費者は食品の成分や添加物の種類についての理解を深め、健康や嗜好に応じた選択ができるようになるでしょう。特にアレルギーや健康志向の高い消費者にとって、この改正は非常に有益です。これらの変更により、食品業界全体が消費者の信頼を得るために、一層の情報透明化と正確な表示を推進していくことが期待されています。
③アレルギー表示の義務化
多くのアレルゲン(アレルギー反応を引き起こすもの)が存在し、それらは卵、エビ、カニ、小麦、そばなどがあります。これらの情報が食品のラベルに誤って表示されると、健康上の問題を引き起こす可能性があります。
国内での食品リコールの約4分の1がアレルギー表示の誤りに関連しているとされています。この問題に対処するため、食品表示の法規制が改正され、新たなアレルギー表示のルールが導入されました。以前は一部の表示を省略することができましたが、改正後は含まれているすべてのアレルゲンを表示することが義務付けられています。
例えば、以前は焼きうどんに含まれる小麦や、マヨネーズに含まれる卵のような、一般的に理解されている情報は表示から省略可能でした。しかし、法改正により、これらのアレルゲンを含む成分は「焼きうどん(小麦を含む)」や「マヨネーズ(卵を含む)」といった形で明示的にラベルに記載する必要があります。
また、パッケージの一括表示欄に「一部に小麦を含む」や「一部に卵を含む」といった形で記載することも求められます。複数の成分や添加物が同じアレルゲンを含む場合、その中の一つに表示をすれば、他は省略可能です。
特に子供向けの食品では、以前からアレルゲンが目立つように表示されることがありましたが、今回の改正により、すべての食品でアレルゲン情報が明確に表示されるようになり、消費者がより安全に食品を選択できるようになりました。
表示義務
表示義務に関しては、特にアレルギーを引き起こす可能性が高く、発症数や重篤度から見て表示する必要性が高いとされる特定の食品が定められています。これらの食品には、以下の7品目が含まれます。
卵:多くの人々がアレルギーを持ちやすい食品で、特に幼児に多く見られるため、表示が義務付けられています。
乳:乳製品に対するアレルギーも一般的であり、乳成分を含む食品には注意が必要です。
小麦:パンや麺類など、広く使用される食品のため、小麦アレルギーを持つ人にとっては重要な情報です。
落花生:重篤なアレルギー反応を引き起こすことがあり、少量でも危険なため、必ず表示が求められます。
そば:そばアレルギーは一部の人々にとって非常に深刻であり、表示が必須とされています。
えび:甲殻類アレルギーの中でも特に発症が多く、表示が必要です。
かに:えびと同様に、甲殻類アレルギーの原因となるため、表示が義務付けられています。
これらのアレルゲンに対する表示義務は、消費者が安全に食品を選択できるようにするために、法的に強制されています。表示がしっかりと行われることで、消費者は自分や家族の健康を守るために、正確な情報に基づいた判断ができるようになります。
任意表示
任意表示の食品については、アレルギーの症例数や重篤な症状を持つ人々の数が一定程度存在し、継続して報告されていますが、特定原材料として表示が義務付けられている食品に比べると、その数は少ない状況です。これらの食品に対するアレルギー表示の義務化については、今後さらに詳細な調査と研究が必要とされており、将来的に表示義務の対象となる可能性があります。
現在、任意表示の対象となっている食品には、以下のようなものが含まれます。
いくら:魚卵アレルギーを持つ人々がいるため、注意が必要です。
キウイフルーツ:果物アレルギーの一つで、特に口腔内の症状が現れることが多いです。
くるみ:ナッツ類のアレルギーの中でも重篤な症状を引き起こすことがあります。
大豆:幅広い食品に使用されており、アレルギー表示が推奨されています。
カシューナッツ:ナッツアレルギーの原因として知られ、注意が必要です。
バナナ:果物アレルギーの一つであり、食べた際にアレルギー反応を起こすことがあります。
やまいも:口や喉にかゆみを引き起こすことがあり、アレルギーの原因となります。
もも:果物アレルギーの一つで、症状の重さは個人によって異なります。
りんご:広く消費されている果物ですが、アレルギーを引き起こすことがあります。
さば:魚介類アレルギーの一種で、表示が推奨されることがあります。
ごま:アレルギー反応を引き起こすことがあり、表示が推奨されています。
さけ:魚介類アレルギーの一つであり、アレルギーのリスクがあります。
いか:魚介類アレルギーの一種で、特に注意が必要です。
鶏肉:肉類アレルギーの原因となることがあり、注意が必要です。
ゼラチン:さまざまな食品に使われており、アレルギーの原因となることがあります。
豚肉:肉類アレルギーの原因となることがあり、特にアレルギーを持つ人には注意が必要です。
オレンジ:柑橘類アレルギーの一つで、食べた際にアレルギー反応を引き起こすことがあります。
牛肉:肉類アレルギーの一種で、重篤な症状を引き起こすこともあります。
あわび:魚介類アレルギーの中でも重篤なアレルギー反応を引き起こす可能性があります。
まつたけ:キノコアレルギーの一つで、アレルギー反応を起こすことがあります。
これらの食品に対するアレルギー表示は、義務化されていないものの、消費者が安全に食品を選択できるようにするために、表示が推奨されており、事業者が表示する際には細心の注意が求められます。今後、さらに調査が進むことで、これらの食品が特定原材料として指定されるかどうかが検討されることになります。
④栄養成分表示の強化
食品表示法の改正に伴い、加工食品や添加物における栄養成分の表示が以前は任意であったものが現在は必須となりました。
表示を義務付けられている栄養成分
・エネルギー(カロリー)
・たんぱく質
・脂質
・炭水化物
・食塩相当量
これまでは、製品に含まれる食塩量がナトリウム量としてラベルに記されていました。しかし、新たな規定により、これからは食塩相当量としての表示が必須になります。
さらに、ラベルに任意で表示できる成分には、飽和脂肪酸、食物繊維、糖質、脂質、コレステロール、ビタミンやミネラルなどがありますが、この中で特に飽和脂肪酸と食物繊維の表示が推奨されています。
⑤加工食品と生鮮食品の区分が統一
食品表示法の施行以前は、食品衛生法とJAS法で食品の分類が異なっていましたが、これが統一され、整理されることになります。
例えば、簡単な加工を施した食品(例: ドライマンゴーなど)に関しては、以前の食品衛生法のもとでは、アレルゲン表示や製造所の所在地表示が義務付けられていませんでした。しかし、新しい基準では、これらが加工食品としての分類に含まれるため、アレルゲンと製造所所在地の表示が必要となります。
⑥製造所固有記号が使えない
以前の規則では、製造所固有記号、販売者の名前、および住所の表示をもって、製造者の名前や製造場所の住所の代用とすることが認められていました。しかし、現在では基本的に製造所固有記号の使用が許可されていません。
基本的には、複数の製造所で同一の製品を生産する場合など、包装材料を共用することによる利点がある際に限り、製造所固有記号の使用が例外的に許可されます。この例外を利用する際には、以下のいずれかの情報を製品に表示する必要があります
・製造所の所在地などの情報を要求された際に応答する担当者の連絡先を表示
・製造所の所在地などを掲載したウェブサイトのURLを表示
・当該製品を生産している製造所の所在地などを表示
ただし、業務用食品の場合は、製品が複数の製造所で製造されるかどうかに関わらず、製造所固有記号を使用することができ、上記の表示要件は適用されません。
⑦小さい食品の表示を省略しない
商品の表示面積が30平方センチメートル以下の小さなサイズであっても、以前は保存方法、消費期限または賞味期限、アレルゲン、L-フェニルアラニン(必須アミノ酸のひとつで、脳と神経細胞間の信号を伝達する役割を持つ神経伝達物質として働く)含有について省略することが許されていました。
改訂された新しい規定により、これらの情報の省略は不可能となりました。この変更により、たとえ表示面積が30平方センチメートル以下であっても、商品の名称、保存方法、消費期限または賞味期限、含まれるアレルゲン、L-フェニルアラニンを記載します。さらには、食品関連事業者の名前や住所などの情報を必ず記載しなければならなくなりました。
⑧加工食品の原産地の表示が必須
以前の食品表示法では、漬物など特定の加工食品に限り、使用されている原料の産地を表示する必要がありました。しかし、改正された食品表示法の下では、原則として全ての加工食品で最も使用量が多い原材料の原産地の表示が必須となりました。表示は、原材料の使用量が多い順で行われ、最初にある材料の原産地が括弧内に示されます。
まとめ
食品表示法とは?
食品表示法とは、消費者が安全で身体によい食品をわかりやすく選べるように、食品の安全性や機能性に関する表示について定めた法律になります。
食品表示法のポイント
①機能性表示ができる
②原材料と添加物を区別する
③アレルギー表示の義務化
④栄養成分表示の強化
⑤加工食品と生鮮食品の区分が統一
⑥製造所固有記号が使えない
⑦小さい食品の表示を省略しない
⑧加工食品の原産地の表示が必須
この記事では、食品表示法とは何か、主なポイントについて解説してきました。食品業界に関わる人は、食品表示法を理解しておくことが、消費者の安全性と信頼を獲得し維持するために不可欠といえるでしょう。
FOOD TOWNでは他にも様々な食品業界に特化した内容を随時更新中です!
まずは下記から無料会員登録をお願いします!
お問合せはこちらまで
Robots Town株式会社
〒533-0033
大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目17-5 941号室
TEL:06-4703-3098
関連リンク・資料