news
4月は“国産はちみつ”の旬!広がる国産食品原材料の活用と制度対応コラム
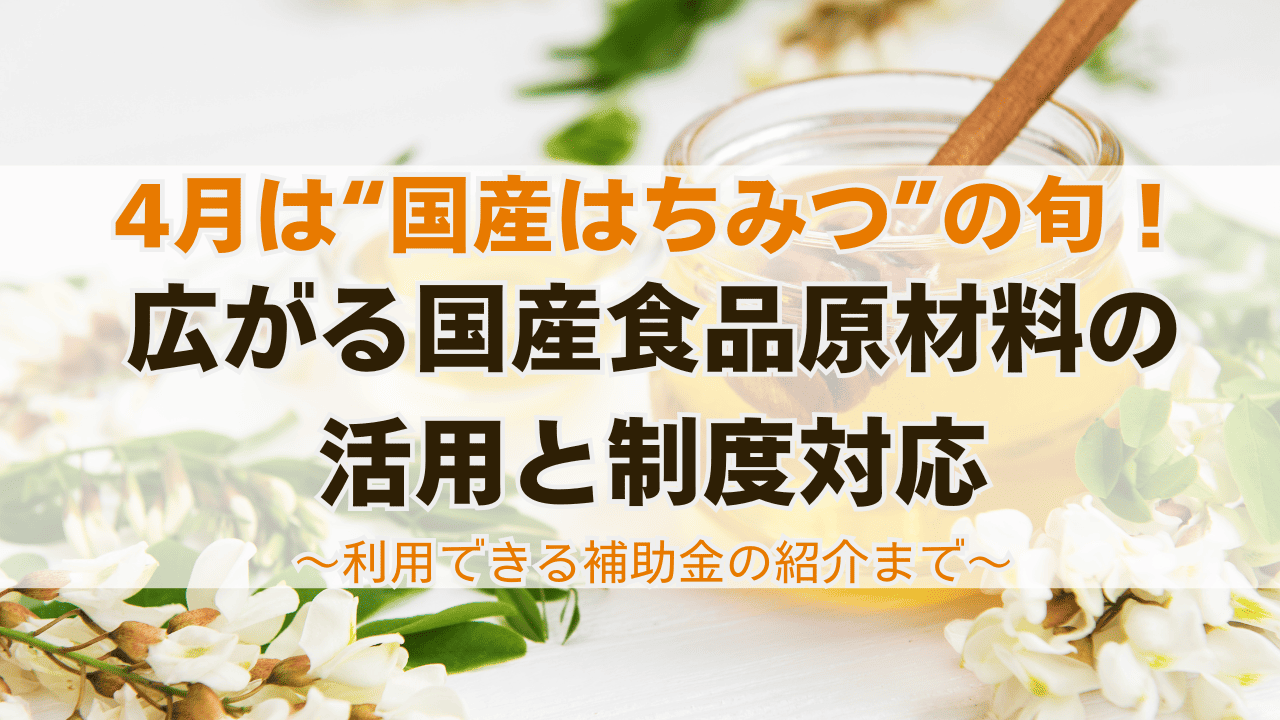
春の訪れとともに、日本各地では“国産はちみつ”の採蜜が始まります。実はこの甘くてやさしい自然の恵みは、いま食品業界でも注目の存在。背景には、2022年に義務化された「原料原産地表示制度」があります。消費者の“安心・安全志向”と企業の“表示対応”が重なり、いま「国産食品原材料」の価値が見直されているのです。本記事では、旬の国産はちみつを入り口に、国産原材料活用のトレンドと支援制度の最新動向をわかりやすく解説します。また、今つかえるおすすめの補助金情報もありますのでぜひチェックしてみてください。
表示義務化がもたらした国産原材料回帰の流れ
原料原産地表示が義務化された背景
2022年(令和4年)4月、すべての加工食品に対して「原料原産地表示」が義務化されました。これは消費者が食品を選ぶ際の“見える化”を促進し、安全・安心に対する意識を高めるための制度です。対象はすべての加工食品で、使用量の最も多い原材料について、その原産地を明示することが求められます。
消費者の意識と食品メーカーの対応
近年は輸入原材料への不安やトレーサビリティの重要性が高まっており、「どこで・誰が作ったのか」を重視する声が強まっています。食品メーカーも、制度対応だけにとどまらず、自社ブランドの信頼性を高める手段として国産原材料の採用を進めています。
国産素材への回帰と“旬”の素材活用
原産地表示をきっかけに、消費者と企業の間で「国産=価値ある選択肢」としての認識が広がりました。特に季節感を活かした国産素材の活用は、商品の差別化や売上促進にもつながります。今回は、4月が旬の「国産はちみつ」に注目しながら、“国産食品原材料”の利用トレンドを読み解いていきます。
4月が旬!国産はちみつの魅力と課題
春の訪れとともに始まる採蜜シーズン
春を迎える4月になると、日本各地でミツバチたちの活動が活発になり、桜やレンゲなどの花から採れる国産はちみつの出荷が始まります。自然の恵みを凝縮したその風味は、まさに旬の味覚といえるでしょう。
国産はちみつならではの魅力
地域や季節ごとの個性ある風味
国産はちみつは、桜やレンゲ、アカシアなど、採れる花の種類によって香りや風味が大きく異なります。その年の気候や採蜜時期によっても味わいが変わるため、“同じはちみつは二度とない”とも言われるほど。地域ごとの個性を楽しめる点が、輸入品にはない大きな魅力です。
酵素やビタミンなどの栄養素が豊富
市販の加熱処理された輸入はちみつと違い、国産はちみつは非加熱や低温処理が一般的です。そのため、ローヤルゼリー由来の酵素やビタミンB群、ミネラルなどの栄養素がそのまま残り、健康食品としての価値も高まっています。
加熱処理を最低限に抑えた品質重視の製造方法
養蜂家が丁寧に手作業で採蜜し、ろ過や瓶詰めまでこだわりを持って製造しているのが国産はちみつの特徴です。過度な加工を避けることで、自然の風味と栄養を最大限に活かす製品づくりが行われています。
生産量の壁と養蜂業の課題
一方で、日本のはちみつ自給率はわずか6〜7%。国内の養蜂業者は高齢化や気象条件の変化、採蜜環境の減少など多くの課題に直面しています。
国産を選ぶ食品メーカーの姿勢
品質やストーリー性を重視し、国産はちみつを採用するメーカーが増えています。特に高級ベーカリーや洋菓子店では、「産地との連携」や「顔の見える素材づくり」がブランド価値に直結しています。
国産食品原材料の使用状況と背景
なぜ今“国産”が求められているのか
消費者の安心・安全”志向、そして地域活性化やサステナビリティの観点から、食品業界では国産原材料へのシフトが進んでいます。
▼ 注目されるポイント
地産地消による地域経済の循環
国産原材料を使用することは、その地域で生産されたものをその地域で消費する「地産地消」の促進にもつながります。これにより地域経済の活性化が期待され、生産者と消費者のつながりも深まります。
輸送距離が短くトレーサビリティが明確
国産素材は輸送距離が短いため、物流の安定や環境負荷の軽減にも貢献します。また、生産・加工・流通の各段階が把握しやすいため、品質管理がしやすく、安心して使用できる体制が整っています。
食品偽装や残留農薬のリスク回避
国産原材料であれば、国内の厳しい農薬基準や衛生管理が適用されるため、食品偽装や残留農薬といったリスクを軽減できます。消費者の信頼を得るためにも、国産素材の活用は有効な手段です。
国産原材料の取扱量と注目品目
農林水産省や各業界団体の調査では、国産原材料の取扱量は増加傾向にあります。特に以下の素材が注目されています:
▶ 米、小麦、大豆(基本穀類)
▶ 果物・野菜(加工食品向け)
▶ 蜂蜜(高付加価値製品)
使える補助金情報
令和6年度補正予算「産地連携推進緊急対策事業」について
令和6年度補正予算で公表された「産地連携推進緊急対策事業」は、食品製造事業者等が産地と連携し、国産原材料の取扱量増加を目指す取組を支援する制度であり、令和7年3月27日(木)より第一次公募が開始されました。
例えば、国産原材料を使用した新商品開発(試作等)にかかる費用や、新商品等の製造に必要な製造ライン上の機器の変更や増設、導入費用などが補助対象となります。ぜひチェックしてみましょう。
お問い合わせ先
令和産地連携推進緊急対策事業事務局コールセンター
0570-000-280
受付時間 9:00~17:30(平日)
※土曜・日曜・祝日・年末年始は休業
関連リンク
事業実施主体(事務局)の公募サイト
https://jmac-foods.com/genzairyou/r6/
農林水産省
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/syokuhin_gen_zairyou.html#T2-1
まとめ
国産食品原材料の活用は、表示義務への対応を超えて、企業のブランド価値や消費者からの信頼を高める戦略的な選択となっています。とりわけ、季節感や地域性を活かせる素材は、商品に独自性とストーリー性を持たせるうえで大きな武器となります。
4月に旬を迎える国産はちみつのように、身近な素材に注目することで、企業としての新たな展開や市場へのアプローチが可能になります。国の補助事業も活用しながら、自社にとって最適な“国産素材の活かし方”を再確認してみてはいかがでしょうか。
FOOD TOWNでは他にも様々な食品業界に特化した情報を随時更新中です!
まずは下記から無料会員登録をお願いします!
お問合せはこちらまで
Robots Town株式会社
〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島6丁目6-17 RIC1st.ビル 501号室
TEL:06-4703-3098
関連リンク・資料