news
【食品工場】外国人雇用に必要な在留資格とは?まず押さえる7種と「技能実習制度」の実践活用ガイドコラム
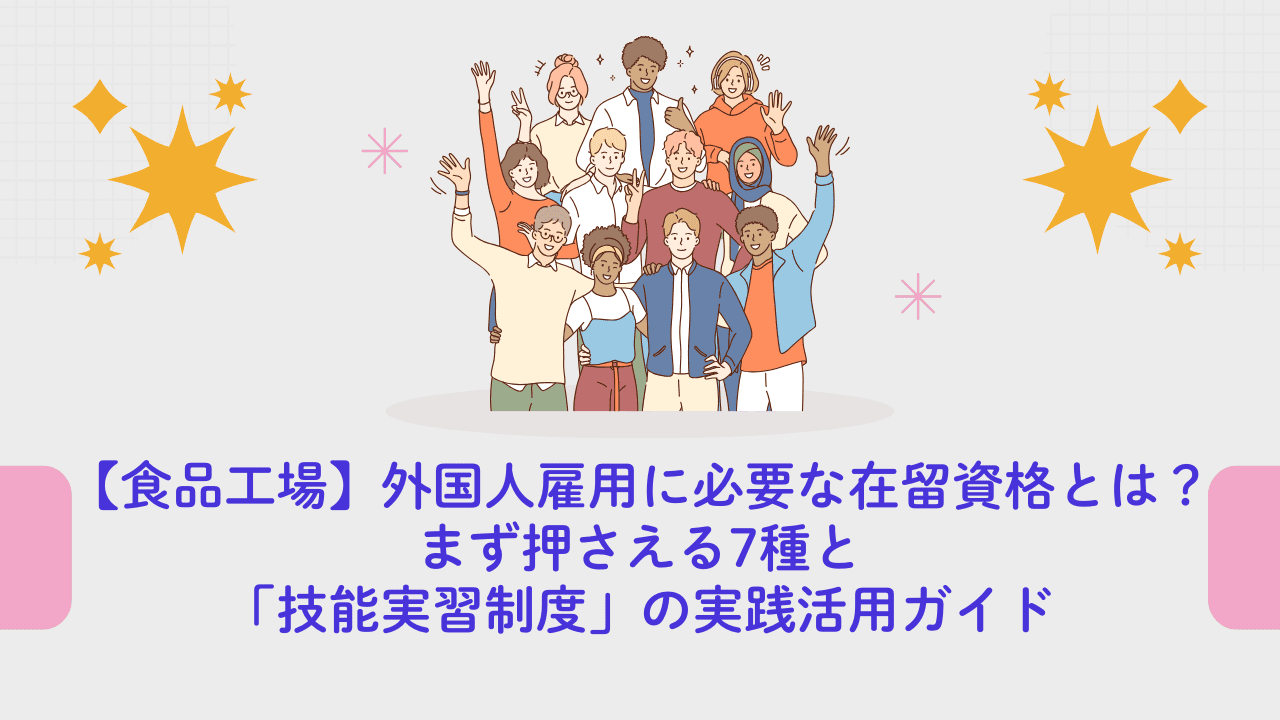
人手不足が常態化している食品工場にとって、外国人労働者の受け入れは重要な選択肢となっています。しかし採用を検討する際、必ず確認すべきなのが「在留資格」です。適切な在留資格がなければ就労が認められず、企業にも罰則が及ぶ可能性があります。
本記事では、食品工場で採用可能な代表的な7種類の在留資格をわかりやすく整理したうえで、実際の現場でも多く活用されている「技能実習制度」にフォーカスし、制度のしくみ・対象職種・運用時の注意点まで専門的に解説します。
★在留資格ごとに必要な書類や帳簿の管理方法を知りたい方は「監査で指摘されないために!在留資格ごとの帳簿・書類管理の基本」をご覧ください。
食品工場で採用可能な在留資格7選
まずは、食品工場において就労可能な在留資格を整理しましょう。
① 技術・人文知識・国際業務
大学卒業以上の学歴を持つ外国人が対象。以下のような業務での採用が可能です。
・商品開発や品質管理
・翻訳・通訳(技能実習生の教育支援など)
・マーケティングや人事などの本社部門
※ライン作業などの単純作業は原則不可。ただし研修目的の短期間従事は例外あり。
② 高度専門職
学歴・職歴・年収などを基にポイント化して評価する制度で、高度人材の受け入れを目的とした在留資格です。
・品質保証、研究開発、海外営業などの高度な業務に対応
・通訳・翻訳を主業務にすることはNGなので注意
③ 特定活動(告示46号)
「技術・人文知識・国際業務」と同様の業務に加え、ライン作業との兼務が可能。教育担当者や技能実習生の指導役を兼ねる現場従事に適しています。
④ 技能実習
日本の技術を学び、母国の発展に役立ててもらうことを目的とした制度。対象となる11職種の食品製造業での就業が可能です(詳細は後述)。
⑤ 特定技能(1号)
2019年から新設された制度で、食品製造業も対象分野。
・ライン作業などの単純作業も可能
・最長5年まで在留可能
・「技能実習」からの移行も可
⑥ 身分に基づく在留資格(永住者、日本人の配偶者等など)
就労制限がなく、自由に職種を選べる点が特徴。採用から戦力化までスムーズなケースが多い。
⑦ 資格外活動(アルバイト)
「留学」や「家族滞在」などの在留資格を持つ外国人が、出入国在留管理庁の許可を得て就労(週28時間まで)できる制度。繁忙期の短期採用に有効。
技能実習制度とは?食品工場での実務に活かすための基礎知識
ここからは、食品工場での導入事例も多い「技能実習制度」について、より詳しく解説していきます。
技能実習制度の目的と特徴
技能実習制度は、日本の技術・知識・技能を開発途上国の人材に移転し、帰国後に母国の発展に活かしてもらうことを目的とした制度です。単なる労働力確保ではなく、「人材育成」が建前となっています。
技能実習には以下の3段階があります:
技能実習1号(1年目)
座学中心。入国後2カ月間の講習を含む
技能実習2号(2〜3年目)
現場での実務を中心に、OJT形式でスキルを習得
技能実習3号(4〜5年目)
一定条件を満たした実習生がさらに在留延長できる
食品製造業での対象11職種
食品製造関連で技能実習の対象となる職種は、以下の11職種(18作業)に限定されています。
※この11職種以外の業務では技能実習生を受け入れることはできません。
実習生の受け入れ方法と流れ
技能実習制度では、企業が直接外国人と契約を結ぶことはできません。原則として監理団体(商工会議所や業界団体など)を通じて受け入れる「団体監理型」が一般的です。以下に、実習生を受け入れるまでの基本的な流れを解説します。
1.監理団体との契約
まず、受け入れ企業は監理団体と契約を結びます。この監理団体は、技能実習生の選定・来日前後の手続き・生活支援・指導などを担うパートナー的存在です。適正な監理団体を選ぶことが、トラブル回避や制度運用成功のカギとなります。
2. 受け入れ計画の作成・申請
受け入れ企業は、どのような業務に何人の実習生を配置するのか、実習内容・教育体制・報酬などを記載した「技能実習計画」を作成し、外国人技能実習機構(OTIT)に申請します。内容に不備があると不認可となるため、監理団体と連携して丁寧に準備する必要があります。
3. 実習生の選定・現地面接
提携する送り出し機関(実習生の母国側の機関)と連携して、現地で面接を行い、実習生を選定します。面接は現地訪問型やオンライン型があり、語学力・適性・意欲などを確認します。また、企業の理念や仕事内容をきちんと伝えることも重要です。
4. 入国〜講習(約2カ月)
日本入国後、実習生は最初の約1〜2カ月間、「入国後講習」を受けます。講習内容には、日本語・生活マナー・法律・労働安全衛生などが含まれており、日本社会に順応するための大切な準備期間となります。この間の生活支援やフォローも企業や監理団体が行います。
5. 実習1号から開始
講習を終えると、企業に配属され「技能実習1号」として実習がスタートします。この段階では基本的な作業習得を目的とし、実習計画に基づくOJT(現場教育)を行います。1号期間を終えると、技能評価試験に合格すれば「2号」「3号」へと進むことが可能です。
実務運用の注意点
実習計画外の作業はNG
ライン工程の中でも、計画に記載されていない業務を実施させると違反となります。
安全衛生教育が必須
危険機械の操作や衛生管理に関する教育を実施・記録すること。
労働条件の明示
賃金・労働時間・残業等の契約は、母国語での明示が必要です。
パワハラ・セクハラ防止策の整備
職場環境の整備は企業の責任です。
技能実習から「特定技能」への移行も可能!
技能実習2号を修了した外国人は、試験なしで「特定技能1号」への移行が可能です。これにより、最長5年の追加就労が実現できます。
人材の定着率が向上し、教育コストの削減にもつながるため、長期雇用を見据える企業にとっては非常に有効な選択肢です。
まとめ
食品工場における人材確保には、外国人の活用が不可欠な時代が来ています。しかし、在留資格の選定を誤れば、不法就労や処罰のリスクにも直面します。
今回は、代表的な7つの在留資格を整理し、とりわけ現場で活用されやすい「技能実習制度」について詳しく解説しました。
✔ 食品製造業に該当するか
✔ 職種と実習内容が一致しているか
✔ 実習生の将来的なキャリアパス(特定技能への移行)も視野に入れているか
これらをチェックしながら、外国人材とともに、安全で働きやすい食品工場づくりを目指していきましょう。
FOOD TOWNでは他にも様々な食品業界に特化した内容を随時更新中です!
まずは下記から無料会員登録をお願いします!
お問合せはこちらまで
Robots Town株式会社
〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島6丁目6-17 RIC1st.ビル 501号室
TEL:06-4703-3098
関連リンク・資料