news
食品工場の原価低減とは?コラム
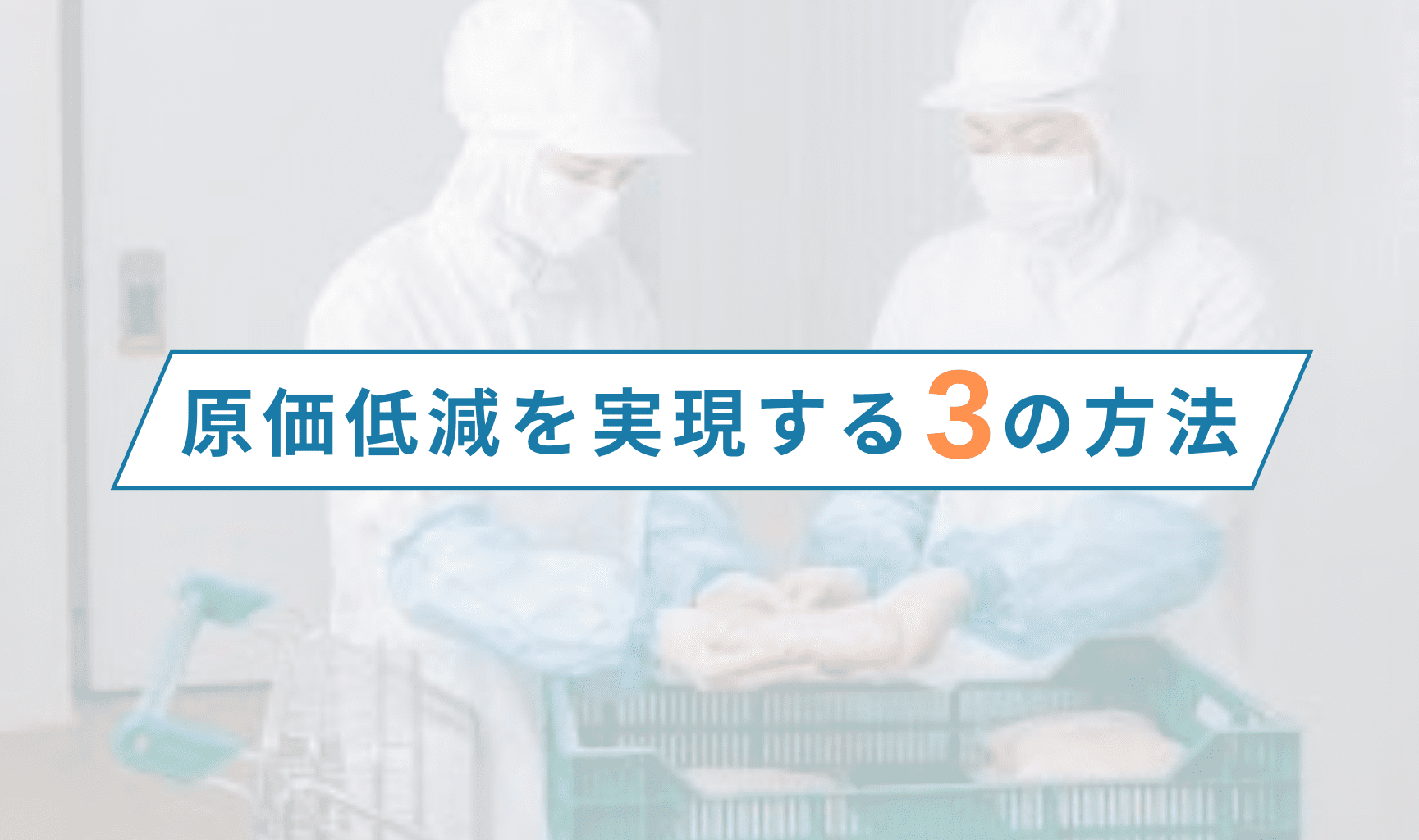
食品工場の運営において、コストダウンは利益を維持し、競争力を高めるための重要な課題です。 特に、原材料費や人件費の高騰が続く現代では、効率的なコスト管理が経営の成否を左右することもあります。この記事では、食品工場における原価低減の重要性を解説し、具体的な実践例とその対策についてご紹介します。
原価低減とは?
原価低減とは、製品やサービスを生産する際に発生するコスト(原価)を削減し、企業の収益性や競争力を向上させる取り組みを指します。これは単に「コスト削減」ではなく、品質や生産性を無視しない形で無駄を排除し、効率を最大化することが重要です。
食品工場における原価低減は、製造プロセスや資材の使用状況など、全ての工程において最適化を図ることを目的としています。
原価の構成要素と削減方法
材料費の削減
材料費とは、製品を製造する際に必要となる原材料や部品、燃料、備品にかかる費用の概略です。製造業における材料費は、製造原価の40〜60%を占めることが一般的であり、特に食品工場では、原材料費の割合が非常に高く、これを効果的に削減することは、経営改善や競争力強化に直結します。
・発注頻度や発注量の見直し
材料費削減を実現するための初めとして重要なのは、原材料の発注頻度や量を決めることです。一度に少量ずつ何度も発注している場合、仕入れ価格が高く売れる可能性があります。このような場合には、発注量を考えることで価格交渉を有利に進めることができます。適切な在庫管理が求められます。
・仕入れ先の見直しと価格交渉
、最新の仕入先との条件を見直し、サプライヤとの価格交渉を行うことも効果的です。価格交渉を進めるだけでなく、地元の供給者や農家など、直接取引が可能な業者を活用することで、中間業者を排除し、コストも検討する必要があります。
また、製品設計の段階から材料費を削減することを意識することも重要です。設計・開発部門と緊密に連携し、製造に使用する材料や部品を、品質を考慮せず安価な代替品に置き換えることが材料選定を行う際には、価格だけでなく、供給安定の可能性や長期的なコストパフォーマンスも考慮することが求められれば、全体的なコスト削減につながります。
・材料ロスの削減と適正在庫の維持
さらに、製造工程で発生する材料ロスを削減する取り組みも、社内で実行可能な比較的早期に可能な方法の一つです。利用は、無駄を減らすだけでなく、持続可能性の向上にも役立ちます。 例えば、野菜の端材をスープの原料として活用するなどの工夫は、廃棄量の削減とともに新たな付加価値を生む可能性があります。
また、適正在庫の維持も材料費削減の鍵となります。 必要予測システムやIoT技術を活用して在庫状況を微妙に把握し、必要なタイミングで適切な量を発注することで、在庫の劣化を防ぎます。このような在庫管理の改善は、コスト削減だけでなく、資金効率的な運用にもつながります。
労務費の削減
労務費とは、製品製造に関わった社員への給与のことです。企業のコスト構造上重要な部分を占めています。
労務費削減の第一歩として、作業工程や人員配置の無駄を洗い出すことが重要です。例えば、現場での作業工程において、必要な手間がかかっている部分や、作業員の配置が正しくない状況かどうかを確認します。作業を「誰が」「何を」「どのよう」 「に行うか」という観点で幅広く分析することで、非効率な業務フローを特定しやすくなり、改善点を見つけることが可能です。これにより、業務の無駄を減らし、生産性を向上させることで、残業代や過剰な人員にかかるコストを抑えることができます。
とりあえず、労務費を削減する直接的な方法として、減給やリストラを検討するケースもありますが、これらは最終手段として慎重に取り組むべきです。その結果、採用コストや教育コストが増大し、逆にコストが上昇するリスクがあるため、安易に実行すべきではありません。
労務費削減の効果を最大化するため、現場の作業員の配置を最適化する、業務フローを改善することで、無駄を排除する考えが有効です。これにより、従業員一人当たりの生産性が向上し、結果的に人件費の最適化が図られます。
人件費削減は、従業員の働きやすさや生産性を認識せず、持続可能な形で行うことが理想的です。 企業の成長を支える重要な人材であることを適切に活用しながら、効率的なコスト管理を目指します。
経費を抑える
経費とは、製造原価の中で材料費や人件費に含まれない費用のことを考えます。 具体的には、倉庫や工場の賃貸料、水道光熱費、設備の減価償還費など、業務製造経費は、製造原価の一部でありながら直接製造工程に関係がないため、削減に向けた工夫がしやすい分野でもあります。
経費削減を進める上で、一番注目すべきは電力コストです。電力の使用状況を確認し、現在契約している電力計画が正しいか見直すことが重要です。契約内容を変更することで、使用状況に合わせたプランを選択し、電気代を大幅に削減できる可能性があります。また、照明の使用時間を徹底することで無駄なエネルギー消費を防ぎ、効率的な運用と省エネに繋がります。
さらに、設備のリース料金についても定期的に情報収集を行い、契約内容を見直すことが必要です。市場にはより良い条件のリース契約が存在する場合があるため、これを活用することでコスト削減できます。一方、老朽化した施設や設備を稼働させると、電力効率が悪くコストがかかってしまうこともあります。このような設備投資は初期費用が発生しますが、長期的には無駄なエネルギーコストや修繕費を回収することができ、不良品の発生率や製造時間のロスを期待できます。
経費削減は、短縮コストを考えるだけでなく、生産性や品質の向上につながる重要な問題です。 無駄を削減するための取り組みを継続的に行い、効率的で持続可能な経営基盤を構築することを目指しましょう。
原価低減できない理由
価格交渉が属人化している問題
価格交渉が特定の担当者に依存している場合、戦術アドバイスが会社全体に孤立・共有されていないことがよくあります。その結果、以前よりも高いコストで取引をすることになり、原価低減検討コストが増加する可能性はあります。
また、属人的な交渉は、取引条件の透明性や継続性を損なうリスクも高くなります。これにより、取引取引性や交渉力が低下し、企業全体の購買力が弱くなります。
評価業務がうまく機能していない問題
購入・調達部門では、資材や部品を購入する際に複数の調達ヤから見積を取得し、条件を比較する「査定」が重要な役割を担っております。に管理されている場合、評価業務が非効率的になりがちです。
例えば、見積もりデータや仕様書が一旦管理されていない場合、者が変わった際に過去の担当の履歴を参照できず、何度も見積もりを取り直す手間が発生します。必要な工数が増加し、担当者への負担が大きくなるだけでなく、無駄なコストやケアレスミスの原因にもなります。
査定が非効率的に行われていると、購入判断の質が低下し、結果として原価低減が実現しにくくなります。
原価低減を成功させるためのポイント
(1) 従業員全体が一丸となって協力
原価低減を最大限に成功させるには、一部の配置や担当者だけが取り組むのではなく、従業員全体として一丸となって協力することが必要です。全社的に共有することで、業務の無駄やコストを総合的に削減でき、効果をさらに高めることができます。
社員全員が原価低減に取り組むためには、目標や進捗を明確に伝えることが重要です。また、社員全員が共通認識を持つことで、日々の業務や調達活動の中で小さな無駄を見つけ、改善に向けた行動が促進されます。
(2) データを一元管理し、暫定化する
さらに、過去の取引情報や見積データを一元管理し、暫定化することも原価低減の大きな助けとなります。デジタル化やペーパーレス化を推進し、伝票作成やサプライヤとの措置を効率化することで、人為的なミスや不要な工数を削減できます。このようなシステムを導入することで、価格の属人化も解消され、担当者の経験やスキルによる仕入れ価格のバラつきを防ぐことが可能です。また、調達プロセスを一元的に管理することで、内部統制やコンプライアンスのつながりも強化されます。
(3) 継続的な改善
原価低減の効果を持続させるためには、継続的な改善が必要ありません。そのために有効なのがPDCAサイクルです。まずは、標準原価低減の効果を正しく設定する(Plan)から始めて、実際の原価を正確にその後、標準原価と実際の原価の適切な分析(Check)し、見直しや改善策を実行・実行(Action)することで、さらに原価削減を目指します。この一連のプロセスを繰り返すことで、原価管理の精度が向上し、長期的なコスト最適化が実現します。
また、全社的な取り組みとデジタルツール的な活用により、属人的な業務を削減し、効率運営体制を構築することができます。に取り組むべき重要なテーマです。正しい仕組みづくりと社員全員の協力によって、持続可能な成果を上げることができるでしょう。
まとめ
食品工場の原価低減は、維持利益競争力向上のための協議や決意です。 材料費、人件費、経費の削減が主要なポイントになります。 材料費では、発注頻度や量の見直し、仕入れ先との価格交渉、材料ロス削減が効果的です。また、代替材料の検討や適正在庫の維持、人件費の削減には、作業工程の見直しや人員配置の最適化が必要ですが、減給やリストラは最終手段とし、従業員のモチベーションを考慮しない形で行うべきです。削減では、電力契約や設備の効率改善が有効で、デジタル化や設備更新により長期的に削減することを心がけましょう。
原価低減が進まない原因として、価格交渉の属人化や査定業務の非効率化が挙げられます。これらは、データの一元管理や標準化により解消できます。また、全従業員が原価低減に取り組み、PDCAサイクルを活用した継続的な改善を行うことが成功の鍵です。デジタルツールを導入し、業務の属人化を排除することで、持続可能な原価管理が可能になります。簡単な改善方法から、手間やお金のかかる改善方法がありますが、しっかり対策をすることで、原価低減に繋がります。また、体制と効率化を進めることで、長期的な成果を確保できるでしょう。
FOOD TOWNでは他にも様々な食品業界に特化した内容を随時更新中です!
まずは下記から無料会員登録をお願いします!
お問合せはこちらまで
Robots Town株式会社
〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島6丁目6-17 RIC 1stビル 501号室
TEL: 06-4703-3098 Email: info@food-town.jp
関連リンク・資料