news
なぜ“同じクレーム”が繰り返されるのか?──食品工場が今すぐ見直すべき現場の5つの視点コラム
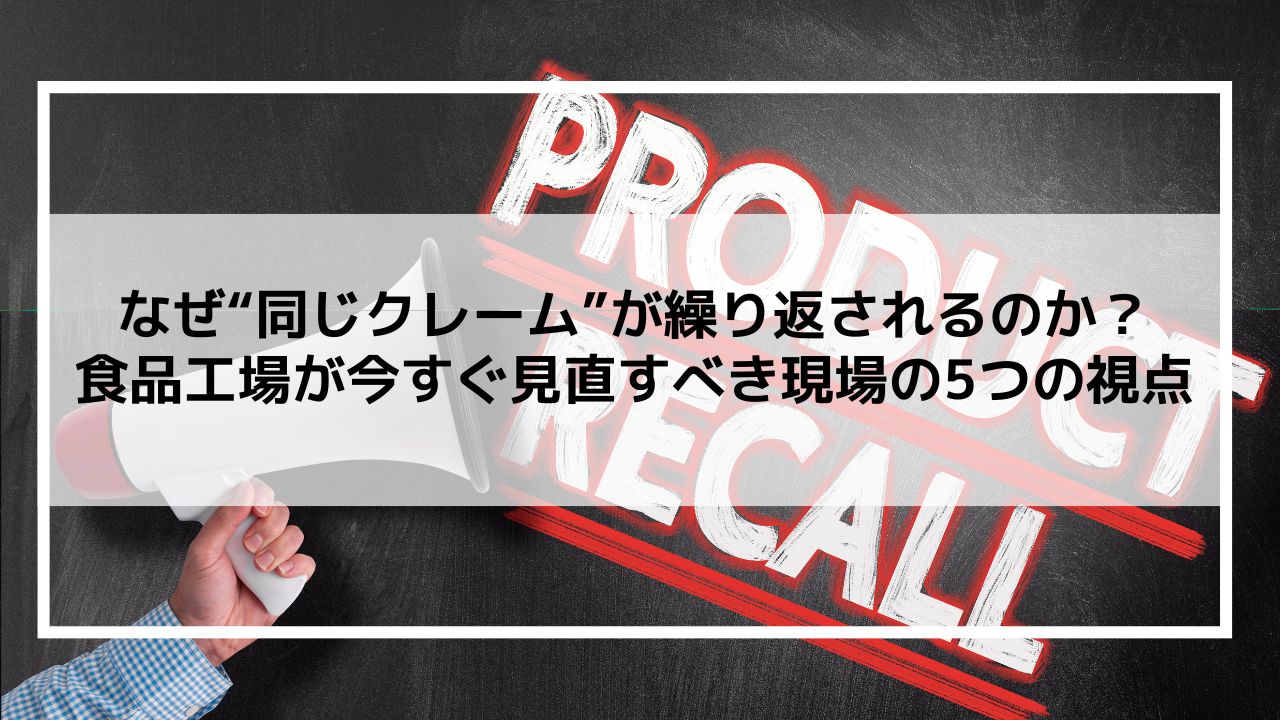
「現場ではしっかりチェックしているのに、またクレームが来てしまった……」
そんな経験はありませんか?
FOOD TOWNをご利用いただいている食品工場の皆さまからも、「再発防止を徹底しても繰り返し発生するクレームへの対策」に関するご相談が増えています。
本記事では、単なる“仕組み化”や“チェック強化”だけでは防ぎきれないクレームの“根本原因”に踏み込み、今日から見直せる5つの視点を解説します。
「クレームの根っこ」を掘り下げていますか?
クレームが発生した際、「作業手順を守っていなかった」「ミスに気づかなかった」などの表面的な原因”だけで処理していませんか?
実際には、「なぜその作業手順が守られなかったのか」「どうすればミスに気づけたのか」といった“構造的な原因”を掘り下げる必要があります。
- チェック項目が多すぎて集中力が持たなかった
- 現場の配置が変更され、確認ミスが起きやすくなった
- 「こうやってるけど、本当は違う」といった自己流の工程があった
こうした本質的な原因を探るには、“5Why分析”(なぜ?を5回繰り返す)や、現場ヒアリングを含めた振り返りミーティングが有効です。
「暗黙の了解」がクレームを引き寄せる
中でも多く見られるのが、「正式な手順とは別に、現場独自のやり方(いわゆるローカルルール)」が存在するケースです。
事例
- 作業マニュアルには「秤量は都度洗浄」とあるのに、現場では「午前と午後で1回ずつ」で通っている
- 「この機械はこうしないと止まる」といったベテランの“感覚”に頼る運用
こうした暗黙知は、引継ぎや異動時に綻びが出やすく、クレームの引き金となります。
マニュアルの定期的な更新と“現場の声”の文書化がカギです。
教育は“伝わる形”になっていますか?
新人教育はしているものの、「覚える量が多すぎて頭に入らない」「外国人スタッフが内容を理解していない」などの声はありませんか?
教育は“伝えた”だけでは不十分で、“伝わった”ことを確認する工夫が必要です。
効果的な工夫
- 手順書に「よくある間違い」「NG例」を明記する
- イラストや動画マニュアルを活用して多言語対応
- 実技テストを通じて理解度を可視化する仕組みを構築
FOOD TOWN掲載企業の中でも、作業映像をスマホで確認できる教育システムを導入したことで、定着率が大きく向上した工場もあります。
「予防」にもう一歩踏み込める仕組みとは
多くの現場では、「確認したかどうか」のチェックリスト運用がされていますが、“なぜ確認するのか”という目的が共有されていないことがトラブル再発につながります。
一歩進んだ仕組み例
- チェックリストの横に「その確認の意義」を記載
- 「手順ミス→どんなクレームになるか」までの因果関係を共有
- クレーム事例から逆算した“注意ポイント集”を定期配布
- こうした小さな工夫の積み重ねが、「作業者の理解」→「意識向上」→「再発防止」へとつながっていきます。
現場の“気づき”が埋もれていませんか?
意外に見落とされがちなのが、「現場でヒヤリとした経験」や「ちょっとした違和感」の扱いです。
これらは、実はクレームの“予兆”であり、活かせば大きなトラブルを未然に防げます。
よくある課題
- 「報告するほどではない」とスルーされている
- 報告しても改善に反映されないため、声が上がらなくなる
FOOD TOWNでもご紹介しているように、ヒヤリハットを簡単に共有できるLINE連携システムや、匿名で投書できる社内フォームなどを導入している企業では、改善提案の質と量が大きく変わっています。
まとめ
設備や仕組みを整えても、同じクレームが繰り返される――
その背景には、現場の理解不足、教育のすれ違い、声を上げにくい環境があるかもしれません。
FOOD TOWNでは、現場の声に寄り添った設備提案や、クレーム低減に寄与する改善事例を多数紹介しています。
ぜひ、貴社の現場でも「クレームを“学び”に変える文化」を育てるヒントとして、本記事をご活用いただければ幸いです。
FOOD TOWNでは他にも様々な食品業界に特化した内容を随時更新中です!
まずは下記から無料会員登録をお願いします!
お問合せはこちらまで
Robots Town株式会社
〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島6丁目6-17 RIC 1stビル501号室
TEL:06-4703-3098
関連リンク・資料