news
食品工場の業務負荷を“見える化”する方法とは?現場改善の第一歩コラム
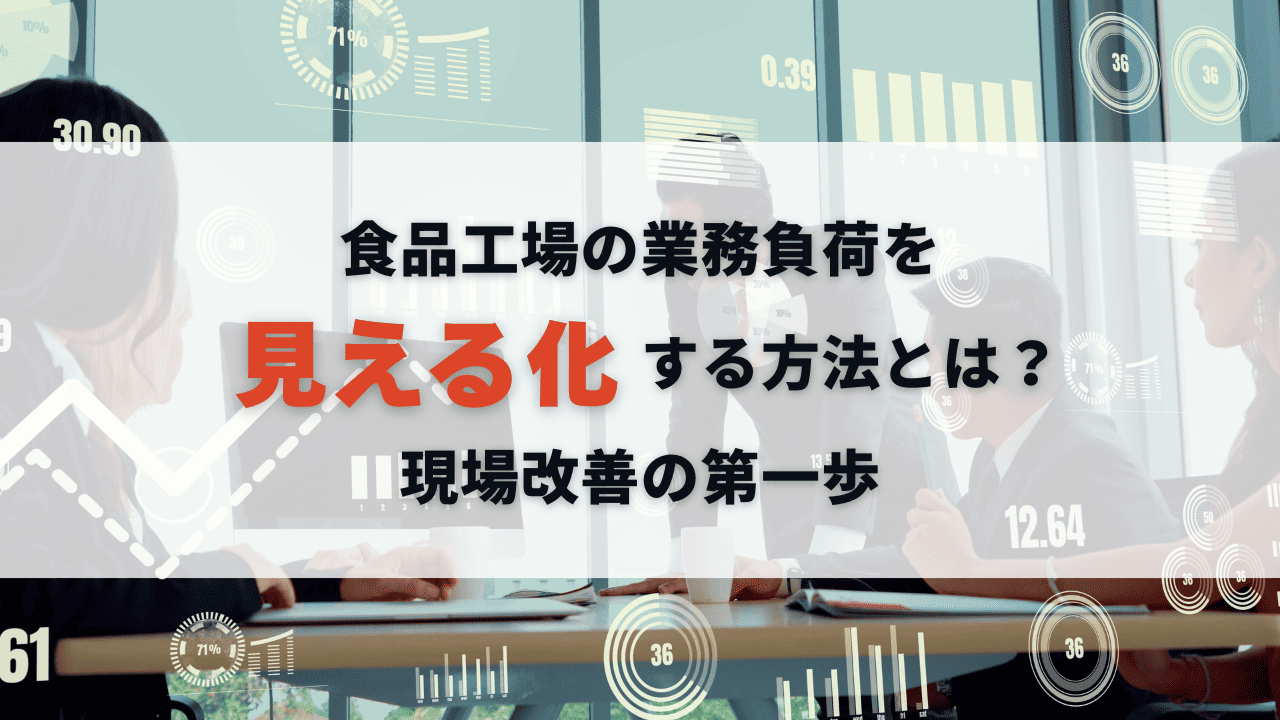
人手不足や慢性的な残業に悩まされる食品工場。改善の第一歩は、「どこに、どれだけの業務負荷が集中しているのか」という情報を正確に把握することです。感覚や経験に頼る運用では、真のボトルネックを見落としかねません。この記事では、業務負荷の“見える化(可視化)”に注目し、どのように業務効率化や生産性向上、働き方改革に役立てられるのか、ビジネスの現場に活かせるノウハウをわかりやすく紹介します。
業務負荷の見える化(可視化)とは?
業務負荷の“見える化”=業務量を定量的に把握すること
業務負荷の可視化とは、各工程や作業にかかる時間・頻度・必要人員・トラブル発生頻度などをデータで「見える」状態にすることです。これにより、仕事の流れやフローを視覚的に把握しやすくなります。このような情報を資料として社内で共有できる状態にすることで、社員全体で現在の会社の状況を理解し、課題解決につなげていくことが可能です。
可視化の主な目的
- 作業のムリ・ムダ・ムラを発見し、ナレッジとして共有
- タスクの偏りを数値で洗い出すことでリスクを低減
- 各部門が協力しながら改善策を検討し、成果につなげる
属人的な管理ではなく、データに基づいた適切なマネジメントへと転換することが、食品工場における可視化の基本であり、DX推進の第一ステップでもあります。
可視化のための具体的な方法
1. 作業日報の電子化とデータ化
紙の作業日報を電子化し、ITツールやクラウドサービスを使って情報共有することで、作業時間・中断時間・エラー発生回数といった情報を誰でも簡単に確認できます。
導入のポイント
- 無料トライアルなどを活用して最適な管理ツールを選定
- 自社の業務内容に応じたテンプレートを作成・配分
- 社員の入力工数を減らし、運用の継続性を重視
2. 工程ごとの工数分析
作業の内容を洗い出し、業務ごとに必要なリソースを明らかにします。これにより、現場の課題や改善点を部門ごとに明確化できます。
活用例
誰が、いつ、どの工程に関わっているかを一覧に
コスト・時間・人材のバランスを最適化し、成果に直結
可視化された情報をエクセルやレポートでまとめ、全体像を社内で共有
3. センサーやIoTによる稼働データの取得
IoTの活用は、食品工場の業務改善において非常に有効です。設備稼働の実態を可視化することで、作業工程やタイミングの「ズレ」に気づくことができます。
主な導入機器
- タグやセンサーを用いた従業員の動線把握
- システム上で稼働・停止・異常を自動記録
- マーケティング部門や顧客対応の連携も含めたデータ分析
可視化のメリットとは?
1. 作業効率の改善と業務効率化
作業の流れや課題を見える化し、プロセス全体を再設計することで、業務のスムーズな進行や負荷軽減が可能になります。これにより、現場のモチベーションも高まりやすくなります。
2. 人員配置の最適化
それぞれの業務負荷を洗い出し、適材適所の人材配置ができるようになります。タスクの重複や過不足も減らすことができ、社内全体の稼働効率が上がります。
3. 残業や負担の平準化
視覚的に業務を把握することで、負担の偏りが明らかになります。チームで配分を見直すことで、業務の負荷を均等化し、社員のモチベーション低下や退職のリスクを防ぐことができます。
4. 教育の標準化とノウハウ共有
教育マニュアルの作成やOJTの可視化により、新入社員への対応がスムーズになります。進め方や注意点を全社で統一することで、属人化を防ぎ、誰でも同じ品質の教育を行えるようになります。
5. 組織全体での改善意識向上
データの可視化により、経営層と現場の意識を合わせ、共通の課題に取り組める体制が構築されます。改善点の「見える化」は、部門を超えた情報共有や連携にもつながります。
可視化による改善事例3選
事例①|人員配置を見直し、繁忙時間のバランス改善
背景
業務量の偏りが大きく、部署ごとに負荷が分散されていなかった。
取り組み内容
作業時間をエクセルで可視化し、タスクの配分を再設計。
結果
各部門の役割が明確になり、モチベーションの向上とともに生産性もアップした。
事例②|IoT導入でトラブル時間を短縮
背景
設備故障の原因が属人的で、情報がうまく共有されていなかった。
取り組み内容
IoTを導入し、トラブル時の情報をリアルタイムで共有。
結果
コミュニケーションロスが減り、対応速度が向上。顧客からの信頼も高まった。
事例③|教育担当の負荷を可視化し、離職率改善
背景
教育担当者のタスクが多く、新人のフォローが不十分だった。
取り組み内容
教育フローを文書化・共有し、研修内容を統一。
結果
研修内容のばらつきがなくなり、離職率が大幅に改善された。
可視化導入の注意点3選
業務の可視化は大きなメリットをもたらしますが、導入にはいくつかの注意点もあります。失敗を防ぎ、効果を最大化するために、以下の3つのポイントを押さえておきましょう。
ツールやシステムの“使い勝手”を軽視しない
可視化に用いるITツールやサービスは、現場の運用にフィットしているかが重要です。高機能でも、社員が使いこなせなければ意味がありません。無料トライアルやテスト導入を通じて、使用感や操作性をしっかり評価しましょう。
情報が“見えるだけ”で終わらないようにする
可視化によって課題を「見える化」しても、対応策が曖昧なままだと改善につながりません。情報共有後は、どの部門が何を行うのかを具体的に明示し、プロセスとして定着させることが重要です。
現場とのコミュニケーションを怠らない
トップダウンで可視化施策を導入すると、現場が「また新しいことが始まった」と感じて抵抗感を持つこともあります。事前に目的や期待される成果を伝え、現場の意見も取り入れることで、協力体制を築きやすくなります。
まとめ
可視化が“やさしい現場”をつくる第一歩
食品工場における業務負荷の可視化は、属人的な判断に頼らず、情報に基づく正しい判断と対応ができる環境づくりにつながります。
ツールやサービスをうまく活用しながら、誰が見てもわかる資料やマニュアルを作成し、従業員一人ひとりが理解・活用できる体制を整えることが重要です。
可視化は、課題を明らかにするだけでなく、社員の意識改革やコミュニケーションの改善、成果の見える化という点でも有効です。多くの企業にとって、今まさに取り組むべき改善策といえるでしょう。
FOOD TOWNでは他にも様々な食品業界に特化した内容を随時更新中です!
まずは下記から無料会員登録をお願いします!
お問合せはこちらまで
Robots Town株式会社
〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島6丁目6-17 RIC1st.ビル 501号室
TEL:06-4703-3098