news
食品ロスとは?企業の事例から学ぶ今からでもできる取り組みコラム
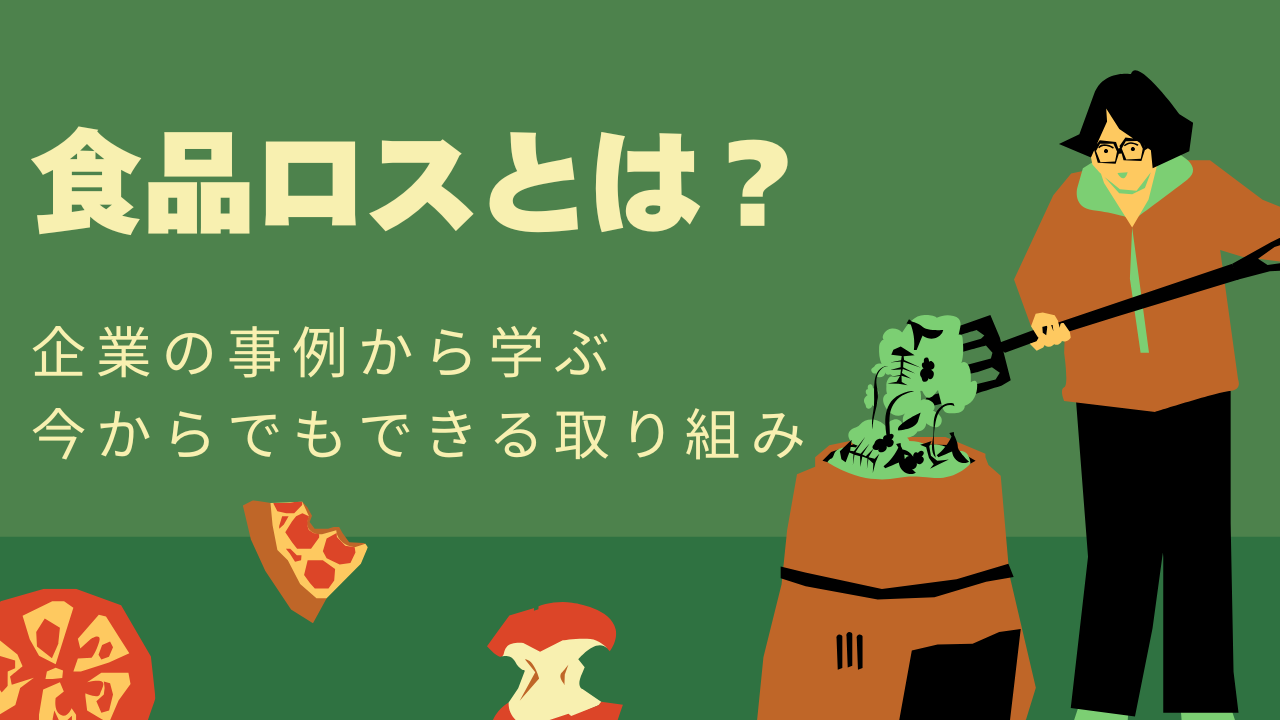
食品を取り巻く課題の中でも、近年とくに注目されているのが「食品ロス」の問題です。食料資源の有効活用、環境保護、そして持続可能な社会の実現に向けて、企業・消費者ともに向き合う必要があります。
本記事では、食品ロスの基本的な考え方から、日本・海外企業の先進的な取り組み、そして今すぐ実践できる対策までを詳しく紹介します。
こちらの記事もおすすめです
★食品ロスとは?【食品工場の用語解説】
食品ロスとは?
食品ロスの定義
食品ロスとは、本来食べられるのに廃棄されてしまう食品のことを指します。農林水産省によると、日本国内の食品ロス量は年間約522万トン(令和3年度)にのぼります。これは国民一人あたり毎日おにぎり約1個分を捨てている計算です。
最新推計から見る改善の兆し
農林水産省の発表によれば、令和4年度の食品ロス量は472万トンと推計され、前年度より51万トンの削減が確認されています。これは企業や自治体、食品製造業を含む関係各所の取り組みが徐々に成果を上げていることを示しています。とくに製造現場では、原材料ロスの可視化や生産スケジュールの最適化、食品ロスに配慮した新商品開発など、ロス削減を意識した工夫が進んでいます。
参考:農林水産省 令和4年度の事業系食品ロス量が削減目標を達成!
世界全体での課題
国連食糧農業機関(FAO)の調査では、世界で生産される食料の約3分の1(約13億トン)が廃棄されています。これは温室効果ガスの排出にも大きく関与し、気候変動や水資源の浪費にも直結する深刻な問題です。
加えて、世界では約8億人が飢餓に苦しんでいると言われており、食品ロスの削減は単なる環境問題だけではなく、人道的な課題の解決にもつながる取り組みなのです。
日本における食品ロスの課題
主な発生源は?
日本の食品ロスは主に以下の2つの場所から発生しています:
事業系食品ロス(約275万トン)
食品製造業、飲食店、コンビニ、スーパーなどから
家庭系食品ロス(約247万トン)
一般家庭での食べ残しや期限切れなど
特に食品製造業では、製造ラインでの過剰生産や、パッケージデザイン変更に伴う既存在庫の廃棄、さらには規格外品の発生などが食品ロスを引き起こす要因となっています。商品化に至らなかった試作品や、需要予測の誤差による余剰在庫の問題も深刻です。こうした課題に対し、多くの企業が工程見直しや在庫管理システムの強化、再加工ルートの確立などによって対応を進めています。
ルールがロスを生む?日本独特の商習慣
日本の食品業界には、独特の商習慣が根強く存在しており、それが食品ロスの原因の一つとなっています。消費者の安心感や信頼性の確保を目的として確立されたこれらの慣例は、品質管理の厳格さやサービスの向上にはつながる一方で、製造や流通の現場に大きな制約をもたらしています。
三分の一ルール
製造から賞味期限の3分の1を過ぎた商品は流通から除外される
過剰包装・高い品質基準
見た目重視での廃棄
これらのルールは消費者ニーズに応える一方で、“まだ食べられる”食品が廃棄される一因となっています。日本の消費者は品質に敏感で、パッケージの小さな傷や形の悪さだけで商品価値が下がる傾向も食品ロスの一因です。
世界の食品ロス対策と動向
フランス:食品廃棄を法律で禁止
フランスでは2016年に「食品ロス禁止法」が施行され、スーパーが売れ残り食品を廃棄することを禁止。代わりに、寄付や再利用が義務付けられています。
また、学校教育にも食品ロスに関する授業を取り入れ、子どもたちへの啓発を早い段階から進めているのも特徴です。
イタリア:寄付にインセンティブを付与
イタリアでは賞味期限切れ直前の食品を寄付した企業に対し、税制上の優遇措置を設けています。これにより食品の再流通が促進されました。
デンマーク:食品ロス専門スーパー「WeFood」
「WeFood」は賞味期限切れやパッケージに傷のある食品を最大50%オフで販売する社会派スーパー。市民の意識を変えるモデルとして注目されています。市民団体が運営している点もポイントで、利益は貧困層への支援に充てられています。
食品ロス削減に取り組む企業事例【日本編】
ローソン:AIと値引きでロス削減
★ AI発注システムを導入し、商品の売れ行きを予測。過剰仕入れを抑制。
★ 賞味期限が近づいた商品を見切り販売(値引き)する仕組みを強化。
この取り組みによって、販売機会の最大化と廃棄コストの削減を両立させています。また、食品ロス削減に協力した加盟店には報奨金制度を設け、モチベーション向上にもつなげています。
日清食品:工場内ロスの見える化
★ 原材料のロス率を工場単位で可視化し、生産現場ごとの改善活動を推進。
★ 商品開発時から「原材料を無駄にしない」設計を行う。
さらに、工場で発生した食品廃棄物は飼料や肥料としてリサイクルされており、循環型社会の構築にも貢献しています。
クラダシ:社会貢献型ECサイト
★ 賞味期限が近い食品や規格外品をオンラインで販売。
★ 売上の一部をフードバンクや災害支援へ寄付。
企業だけでなく、個人も気軽に参加できることが特徴で、“誰でもヒーローになれる”をキャッチフレーズに食品ロス削減と社会貢献の両立を進めています。
ロスゼロ:訳あり商品のプラットフォーム
★ 賞味期限が短い食品、パッケージ不良商品などをお得に販売。
★ SNSやイベントを通じて消費者の意識改革にも力を入れている。
また、製造業との連携により、新たな商品開発(ロスを再加工した商品)も進めており、単なる販売だけにとどまらない革新的な取り組みが進行中です。
明日からできる!食品ロスを減らすポイント
1. 賞味期限と消費期限の違いを理解する
賞味期限
おいしく食べられる目安
消費期限
安全に食べられる期限まとめ:記録は“証拠”になる
造ラインや物流担当者が正確な理解を持つことで、適正な在庫管理と出荷判断が可能になります。「期限が切れた=廃棄」ではなく、製造後の保存条件や流通先での販売期間を考慮して柔軟に運用する体制を整えることが重要です。
IoTを活用した期限管理システムや在庫の動きを可視化するデジタルツールの導入も効果的で、現場から始める食品ロス削減を実現する鍵となります。
2. 過剰生産・規格外品の発生を防ぐ工程管理の最適化
★ 受注予測に基づいた生産計画の策定
★ 規格外品の再加工や業務用転用の仕組みづくり
★ 定期的な生産ラインの見直し
需要と供給のズレを最小限に抑えるため、AI予測モデルやERP(基幹業務システム)との連携を図る企業も増えています。また、ロス品を単純に廃棄するのではなく、リパッケージや二次加工など、活かす選択肢を社内に設けておくことも大切です。
3. 社内販売や外部連携を活用して販路を拡大する
★ 工場直販やオンラインショップでの在庫処分
★ 社員向けの「ロス軽減販売制度」導入
★ フードバンクや福祉団体との提携
製品としての品質に問題がない場合、訳あり商品としての社内販売や寄付による社会貢献がロス削減と企業価値向上の両立に繋がります。また、消費者や関係団体との協力による食品ロスを共有する文化づくりも今後の重要な取り組みと言えるでしょう。
明日からできる!食品ロスを減らすポイント
食品ロスの削減は、環境保全やコスト削減、そして社会的責任の達成につながる重要なテーマです。食品製造業においても、日々の工程を見直すことで大きな効果が期待できます。今回紹介した企業のように、AIやデータ活用による在庫・発注の最適化、工場内ロスの見える化、ロス品の有効活用などは、どの企業にも応用可能な具体的アクションです。
「廃棄はコスト」と捉え、できるところから始める意識改革をしていきましょう。
FOOD TOWNでは他にも様々な食品業界に特化した内容を随時更新中です!
まずは下記から無料会員登録をお願いします!
お問合せはこちらまで
Robots Town株式会社
〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島6丁目6-17 RIC1st.ビル 501号室
TEL:06-4703-3098
関連リンク・資料